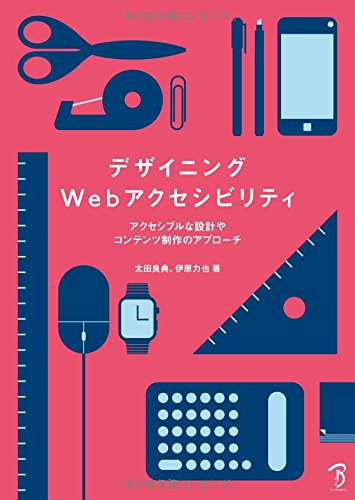「デザイニングWebアクセシビリティ」という本を読みました。
アクセシビリティ、つまり「アクセスのしやすさ」を確保するために、どのようにWebをデザインすればよいかを学ぶことができます。
なんだか難しそうなタイトルで敬遠していましたが、読んでみると、全然堅苦しくなく身近でわかりやすい内容でした。
アクセシビリティはユーザビリティと密接に関わっていますので、ユーザビリティに興味のある方にもおすすめです。
アクセシビリティって障害者だけのためのもの?
アクセシビリティって障害者だけのためのものでしょ?と思っている人もいるかもしれません。
しかし、アクセシビリティを考慮するということは、
- 手にケガをした
- スマートフォンで操作しなければならない
- 通信速度がおそい環境にいる
…などなど、
日常で起こりうるちょっとした壁も考慮したサイトをつくるということ。
アクセシビリティの改善は、普段ウェブを使う誰もが恩恵を受ける事ができます。
Webに慣れてしまっている人がデザインを見直すことができる
ディレクター、デザイナー、プログラマなど、一日中Webに関わっている我々ですが、Webの使い方に慣れすぎてしまっています。そのため、知らぬ間にWebに慣れてないユーザーをおろそかにしてしまっている事が多々あります。
「デザイニングWebアクセシビリティ」では、ユーザーがどんなときに行き詰まってしまうのかという問題点とその解決方法が解説されています。
ユーザー目線に戻る事はWeb制作に欠かせない大切なポイント。
デザインの意図が明確になる
なんとなくデザインしてしまっている部分の「なぜ?」を明確にする事ができます。
例えば、お問い合わせフォームの必須項目に赤い「※」マークが書かれており、必須とされている暗黙のルールがあります。しかし、慣れていない人にとってはそのルールがわかりません。送信ボタンを押すことで初めてエラーということがわかります。
その場合、各項目に「必須」「任意」とテキストでラベルが書かれていれば、どんなユーザーでも分かるお問い合わせフォームになるわけです。
フォームのデザイン一つとっても、アクセシビリティを考慮した理由があるのですね。
デザインの見た目しか考慮しない人に「必須とかわざわざ書いてるのダサいから"※"マークに変えといて」といわれたとしても、ちゃんと上記のような説明があれば納得してもらえると思います。
Webデザインの一つ一つには意味があり、理由を説明できる事が大切です。
特にフォームはユーザーがつまづきやすく、アクセシビリティの改善の余地がありまくる項目なので、このセクションだけのためにも「デザイニングWebアクセシビリティ」を読む価値があると思います。
他にはカルーセルパネルなどの動的コンテンツの作り方についても詳しく言及されているので、理由のないインタラクティブなデザインを求められたときはこの本を武器に戦えるはず。
そんなことでは楽しいWebサイトが作れなくなってしまうじゃないかという声もあるかもしれませんが、実はそれは制作者にとってのエゴで、ユーザーはそこに楽しさを求めていないかもしれません。別のアプローチで多くの人に楽しんでもらえるコンテンツを設計することが大事です。
注意点
詳細な検証方法は載っていないので自分で調べる必要があります。
例えば「ユーザビリティテストを行うと良いでしょう」とあるけど、方法は別の書籍などで調べないといけません。これらの検証方法だけで結構なボリュームの内容になるのでしかたないと思います。
ちなみにユーザビリティテストについては以前読んだ「超明快 Webユーザビリティ」に詳しく解説されていました。
他に何かあったとすれば、表紙の色がチカチカして目に刺さる…ですかねぇ…。
さいごに
スマートフォンが登場した当時、Webデザインは派手で、過度なインタラクションを実装したサイトが多かったように思います。
近年のWebデザインは「印象に残すサイト」というよりは、よりインフラ的な存在となり、使いやすさに重点をおいた傾向が強まっています。ですので、アクセシビリティを考えてデザインすることはこれからどんどん求められると思います。
Web制作に関わる人はぜひ一度手にとって読んでみて下さい。より実践的で、より重要な内容なので常にそばにおいておきたい一冊となるはず。

デザイニングWebアクセシビリティ - アクセシブルな設計やコンテンツ制作のアプローチ
- 作者: 太田良典,伊原力也
- 出版社/メーカー: ボーンデジタル
- 発売日: 2015/07/27
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (4件) を見る